大阪青山大学「公開講座」のご案内
学びで豊かな生活を
大阪青山大学「公開講座」のご案内
2022 年度に、本学園創立 55 周年記念事業のひとつとして実施しました「大阪青山塾 社会人教養講座」は、2 年間にわたりたくさんの方にご受講いただきました。
今年度は、さらに多くの方にご参加いただけますよう、単発講座、受講料無料(入館料、材料費等必要な場合あり)にて「公開講座」として、お子さまからシニアまで、幅広い層でお楽しみいただける講座を実施します。
皆さまのお申し込みを、お待ちしております。
A:「歴史文学講座」、E:「夏休み子ども講座」、D:調理実習「日々の食卓に豆乳をとり入れてみませんか?」、H:「アクティブシニアのためのワクワクトレーニング」は定員に達しましたので、受付を終了させていただきます。たくさんのご応募、ありがとうございました。
令和 6 年度前期 講座一覧
講座紹介
A 文学歴史講座「大阪青山歴史文学博物館」見学と展示解説 ※定員に達したため受付終了となりました
本講座は「大阪青山大学 北摂キャンパス(川西市)」にて開催されます
源氏物語とその美術
紫式部の「源氏物語」は、千年以上の時を経て今なお多くの人に愛される平安時代の文学作品です。この講座では、大阪青山歴史文学博物館が所蔵する源氏物語にまつわる絵巻物等をご覧いただき、大河ドラマでも話題の源氏物語の世界を美術品としての観点からもお楽しみいただきます。
 |  |  |
| 日時 | 7 月 24 日(水)10:30 ~ 12:00 |
| 講師 | 小倉 嘉夫 大阪青山歴史文学博物館 主任学芸員 |
| 受講料 | 無料(ただし博物館入館料として 300 円が必要) |
| 場所 | 大阪青山大学 北摂キャンパス 大阪青山歴史文学博物館(兵庫県川西市) |
| 定員 | 25 名 |
B 心理学入門「学習の心理学」
経験により行動が変わるしくみ、行動を変える方法を考える
本講座では、生活のなかの様々な人間行動について、「学習の心理学」の視点から考えます。経験による行動の変化を「学習」といいます。私たちの生活習慣も感情も学習の影響を受けています。この講座では「学習」の基本的な仕組みや、行動変容(行動を変える)の技法について学びます。
 |  |  |
| 日時 | 7 月 26 日(金)10:30 ~ 12:00 |
| 講師 | 太田 誠 大阪青山大学 健康科学部 健康栄養学科 教授 |
| 受講料 | 無料 |
| 場所 | 大阪青山大学 箕面キャンパス |
| 定員 | 40 名 |
C 幼児期の食物アレルギー
食物アレルギーを持つ子どもが就園・就学に向けて準備しておくこと
小麦、牛乳、卵等々、食物アレルギーを持つお子さまの保護者の皆さまは、日常の食事について留意されていることでしょう。特に就園、就学等による環境の変化がある場合はなおさらです。この講座では、箕面市教育委員会の協力を得て食物アレルギー対応の給食レシピ本を作成した講師が、幼児期の食物アレルギーについてお話しします。社会福祉や教育関係に携わる方にもお聞きいただきたい講座です。
 | 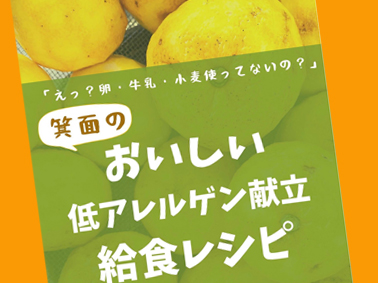 |  |
| 日時 | 8 月 3 日(土)10:30 ~ 12:00 |
| 講師 | 蜂須賀 のぞみ 大阪青山大学 健康科学部 健康栄養学科 准教授 |
| 受講料 | 無料 |
| 場所 | 大阪青山大学 箕面キャンパス |
| 定員 | 30 名 |
D 調理実習「日々の食卓に豆乳をとり入れてみませんか?」 ※定員に達したため受付終了となりました
豆乳マメ知識と豆乳活用術
大豆は「畑のお肉」といわれるほど栄養価が高く、昔から豆腐やきな粉などに加工されてきました。豆乳もそのひとつで、健康維持や美容の効果が期待できる栄養成分が豊富に含まれています。本学では学修の一環として、学生がヤクルトの豆乳を使ったアレンジレシピを開発しました。この講座では近畿中央ヤクルト販売(株)社員の方からも豆乳の話を聞き、アレンジレシピの調理実習をお楽しみいただきます。
 |  |  |
| 日時 | 8 月 21 日(水)10:30 ~ 12:00 |
| 講師 | 須谷 和子 大阪青山大学 健康科学部 健康栄養学科 准教授 |
| 受講料 | 無料(ただし材料費として 500 円が必要) |
| 場所 | 大阪青山大学 箕面キャンパス |
| 定員 | 20 名 |
| 持ち物 | エプロン、三角巾 |
E 夏休み子ども講座「かけっこ教室」 ※定員に達したため受付終了となりました
正しい走り方を知ろう
MLB では日本人選手が活躍し注目を浴びていますが、野球に限らずスポーツをするには正しいフォームが大切です。この講座では、子ども達に正しい走り方を体感していただきます。正しい走り方を身につけることで、タイムアップが図れるほかに、基礎的な身体能力の向上も期待できます。
 |  |  |
| 日時 | 8 月 24 日(土)10:30 ~ 12:00 |
| 講師 | 村田 トオル 大阪青山大学 子ども教育学部 子ども教育学科 教授 |
| 受講料 | 無料 |
| 場所 | 大阪青山大学 箕面キャンパス(リズム室) |
| 定員 | 15 名 |
| 対象 | 幼・保育園年長児 ~ 小学 6 年生児童 |
| 持ち物 | 体育館シューズ(上靴)、汗拭きタオル、飲料水 |
F 日常生活の食事から健康を考える
バランスの良い食事ってな~に?
食事は毎日当たり前のように摂っていますが、その食事は身体に栄養を与えるという非常に重要な役割を果たしています。「健康づくりは毎日の食事から」と言われるように、ただ食べるのではなくバランスを考えて食べることがポイントです。この講座では、栄養バランスが良い食事とは具体的にどのようなものか、について解説します。
 |  |  |
| 日時 | 8 月 28 日(水)10:30 ~ 12:00 |
| 講師 | 高田 守康 大阪青山大学 健康科学部 健康栄養学科 講師 |
| 受講料 | 無料 |
| 場所 | 大阪青山大学 箕面キャンパス |
| 定員 | 40 名 |
G 糖尿病との付き合い方を学ぶ
糖尿病と向き合い充実した生活を
糖尿病治療の基本は「食事療法」「運動療法」「薬物療法」と言われています。食事療法と聞くと、「あれも食べられない。これもダメ」と思われる方も少なくないようです。また「暑いから …」「寒いから …」と、運動することが苦手な方もおられます。薬に関しても「飲み忘れ」「インスリンのうち忘れ」の経験もあるのではないでしょうか。この講座では、糖尿病とうまく付き合う方法についてお話しします。
 |  |  |
| 日時 | 9 月 4 日(水)10:30 ~ 12:00 |
| 講師 | 横田 香世 大阪青山大学 看護学部 看護学科 教授 |
| 受講料 | 無料 |
| 場所 | 大阪青山大学 箕面キャンパス |
| 定員 | 40 名 |
H アクティブシニアのためのワクワクトレーニング ※定員に達したため受付終了となりました
健康のため長く続けられる運動
「健康のために運動しなければ」と一念発起して、ジム通いやランニングをはじめる方もいらっしゃると思います。しかし、急にハードな運動をはじめると、長続きしないことや身体に過度な負担を強いる場合があります。この講座では、年齢に応じた「お家でできる簡単で、健康増進のために効果的な運動」を実際に体感してもらいながらお話しします。
 |  |  |
| 日時 | 9 月 7 日(土)10:30 ~ 12:00 |
| 講師 | 村田 トオル 大阪青山大学 子ども教育学部 子ども教育学科 教授 |
| 受講料 | 無料 |
| 場所 | 大阪青山大学 箕面キャンパス(リズム室) |
| 定員 | 15 名 |
| 持ち物 | 体育館シューズ(上靴)、汗拭きタオル、飲料水 |
I スポーツ栄養学から見た運動と食事の関係
健康寿命の延伸を目指して
健康のために運動やスポーツを始めた方、これから始めようと思っている方におすすめの講座です。健康増進のためには運動に加え、その運動量に見合った適切な食事摂取も重要な要素となります。何をどのくらい、どのように食べれば良いかを学ぶために、今回はスポーツ栄養学の観点から、健康寿命の延伸を目指すための運動と食事の関係についてお話しします。
 |  |  |
| 日時 | 9 月 11 日(水)10:30 ~ 12:00 |
| 講師 | 高木 尚紘 大阪青山大学 健康科学部 健康栄養学科 講師 |
| 受講料 | 無料 |
| 場所 | 大阪青山大学 箕面キャンパス |
| 定員 | 40 名 |
J 特別講演「ガンバ大阪の地域密着活動」
地域住民に愛される地元サッカークラブを目指して
ガンバ大阪は J リーグ発足以来の長きにわたり、トップクラスの人気と実力を誇ってきました。その人気を支える戦略のひとつに「地域密着のホームタウン活動」があります。吹田市、箕面市はじめ近隣の 7 市 3 町で社会貢献(CSR、SDGs)など地域密着型の活動を実施しています。この講座では、J リーグ発足当時からガンバ大阪を支える伊藤営業部長を特別講師に招き “ここだけの話” も交えて講演していただきます。
※大阪青山大学はガンバ大阪のオフィシャルパートナーです
 |  |  |
| 日時 | 9 月 17 日(火)10:30 ~ 12:00 |
| 講師 | 伊藤 慎次 株式会社ガンバ大阪 営業部部長 |
| 受講料 | 無料 |
| 場所 | 大阪青山大学 箕面キャンパス |
| 定員 | 40 名 |
講座早見表
| 記号 | 講座名 | 定員 | 実施日 | 締切 | 講師 | 受講料 (税込) |
| A | 文学歴史講座 「大阪青山歴史文学博物館」見学と展示解説 | 25 | 7.24(水) | 7.19 | 小倉 嘉夫 | 300 円 (入館料) |
| B | 心理学入門「学習の心理学」 | 40 | 7.26(金) | 7.21 | 太田 誠 | 無料 |
| C | 幼児期の食物アレルギー | 30 | 8.3(土) | 7.29 | 蜂須賀 のぞみ | 無料 |
| D | 調理実習 「日々の食卓に豆乳をとり入れてみませんか?」 | 20 | 8.21(水) | 8.16 | 須谷 和子 | 500 円 (材料費) |
| E | 夏休み子ども講座「かけっこ教室」 | 15 | 8.24(土) | 8.19 | 村田 トオル | 無料 |
| F | 日常生活の食事から健康を考える | 40 | 8.28(水) | 8.23 | 髙田 守康 | 無料 |
| G | 糖尿病との付き合い方を学ぶ | 40 | 9.4(水) | 8.30 | 横田 香世 | 無料 |
| H | アクティブシニアのためのワクワクトレーニング | 15 | 9.7(土) | 9.2 | 村田 トオル | 無料 |
| I | スポーツ栄養学から見た運動と食事の関係 | 40 | 9.11(水) | 9.6 | 髙木 尚紘 | 無料 |
| J | 特別講演「ガンバ大阪の地域密着活動」 | 40 | 9.17(火) | 9.12 | 伊藤 慎次 | 無料 |
いずれも講義時間は 10:30 〜 12:00 です。
募集要項
受講に際しての注意事項
・講義日時は、直前に変更になる場合があります。
・自動車、バイクでの登学はご遠慮ください(阪急箕面駅前から無料スクールバスをご利用いただけます)。
・土曜日講座と博物館は、車でも登学可とします(事前にご相談ください)。
・自転車は「学生用駐輪場」に停めてください。
・大学内は全面禁煙です。
・本学へのアクセスは こちら をご覧ください。
気象警報発令時等における講座の取り扱いについて
・箕面市に「特別警報」または「暴風警報」が発令され、午前 6 時までに解除されない時は中止いたします。また、箕面市に「土砂災害警戒情報(警戒レベル 4 相当)」が発表された場合も同様の取り扱いとします。予定通り実施する場合でも、受講者の皆様の地域において警報など発令されている場合は、安全を最優先してください。
キャンセルについて
・急な欠席をされる場合は、その旨ご連絡願います。
・当日体調が思わしくない場合、無理に出席されないよう願います。






