寛容性の涵養を図る小学校社会科授業の開発
| 子ども教育学部 准教授 服部 太 研究分野:社会科教育、社会学 |
「寛容性の涵養」とは、平たく表現すると「異なる考えや、価値観を理解して受け容れる素地を育むこと」となるでしょうか。服部准教授は、異なる考えや価値観から自分自身の見方・考え方を変えていくことに資する社会科授業のあり方について、研究を進めています。
聞き書き:広報室
研究テーマを教えてください
寛容性の涵養を図る小学校社会科授業の開発
どういった内容の研究でしょうか
目的
子どもたちは、異なる考えや価値観をどう理解しようとしているのか
「これしかない」より、「こういう見方・考え方もあるんだ」という考えや価値観を身につけ、他者とのかかわりを楽しむことができるようになったらと思います。
対象
小学校児童
内容
例えば、小学校のある学級に「みんなで仲良く過ごそう」という学級目標があったとします。この学級目標のもと、子どもたちはドッジボールや鬼ごっこに興じます。しかし、学級の中には、ドッジボールや鬼ごっこをしたくない子どもたちだっています。このような子どもたちは、「せっかくみんなで仲良くしようとしているのに、協力してくれない」と非難されてしまうかもしれません。一見、「みんなで仲良く過ごそう」は当たり前のようなフレーズです。その反面、「みんなで仲良く過ごそう」の学級目標が強く履行されればされるほど、全体に同調しないと見なされた子どもたちは排除の対象となってしまうこともあります。つまり、当たり前のような考えや価値観の中には、実は当たり前でないことだってあるといえます。このことは学級だけに限りません。学級以上に多様な人々が生活する社会においては、ある人にとっては当たり前でも、他の人にとっては当たり前でない考えや価値観はたくさん存在します。
以上のことをふまえて「それって、本当(に適切)?」と疑問をもち、「他の人からしたら ◯◯ という見方・考え方もあるんだ」と自分の考えや価値観を相対化したり、再構築したりしていく小学校社会科授業の開発をめざしています。
 | 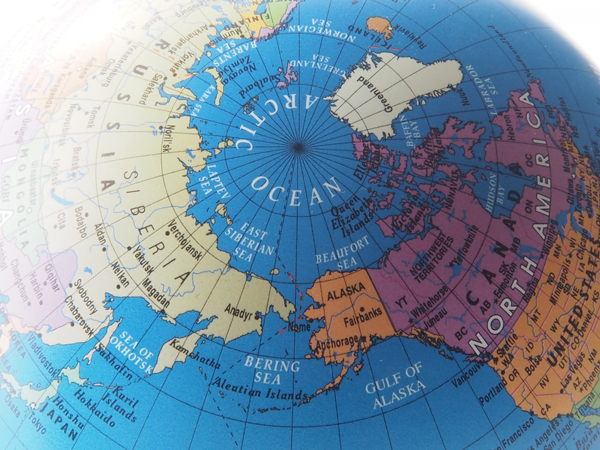 |
研究を進められる中で、今どのような課題や成果が見えていますか?
成果のアセスメントはこれからです。課題はたくさんあります。そのひとつとして、近い将来、自分の教え子たちの追跡調査を行い、小学校社会科授業のあり方について省察ができたらと考えています。
 |  |  |









