内定者の声
就職活動を終えた先輩たちに、内定獲得までの道のりを振り返ってもらいました。
健康科学部 健康栄養学科
【食品メーカー】岡部 正樹 さん 株式会社 阪急デリカ
 | 健康科学部 健康栄養学科 2024 年 3 月卒業 大阪府立園芸高等学校出身 就職活動期間:2023 年 4 月 〜 6 月 |
小学生の頃、色々な食品アレルギーを持っており、食品について勉強をしたことがきっかけで、食に関心を持つようになりました。進んだ高校が農業高校だったため、食という分野について多く触れることとなり、食への関心がさらに高まりました。
就職先の業種を選んだ理由
食についてより深く学ぼうと大学で管理栄養士の学科に進み、学んでいく中で、食の専門知識を活かして食品の企画・開発をすることに興味が湧いてきたため、食品メーカーへの就職をめざしました。
私の就活キーワード
「量」です。
管理栄養士課程に必須の臨地実習が 3 年次の 3 月にあったため、4 年次になるまで就活を始められませんでした。3 月中に募集を締め切る会社も多くあり、最初から選択肢が狭くて大変だなと感じました。そこで、少しでも興味を持った会社の説明会や面談にはできる限り参加して、可能性を広げようと努力しました。このことが、就職試験の場数と経験を得る結果となり、後の内定につながったと思います。
私の経験では、どんなに面接練習しても最初の数回は緊張してうまく話すことができませんでした。緊張は回を重ねるごとに軽くなっていくので、早い段階で会社の面接を経験しておくのが良いと思います。第一志望の会社である必要はないので、少しでも気になったところの採用試験にはどんどんチャレンジしていくことをお勧めします。
進路支援センターのサポート
進路支援センターでは、主に面接練習の相手をして頂きました。こちらがお願いした分だけ、何度でも繰り返し練習に付き合って頂けたので、自分の満足いくまで練習を重ねることができ、自信につながりました。
 |  |  |
今後の目標・メッセージ
最初は職場の色々な仕事を経験することから始まります。早く仕事に慣れて、商品企画や開発の部門に行けるよう、頑張りたいです。
健康栄養学科の場合、3 年次末の臨地実習からの就活スタートで慌ただしい数ヶ月になりますが、そこを乗り越えて納得のいく内定を手に入れてください。
【医療】佐々木 透穂 さん 医療法人 医誠会
 | 健康科学部 健康栄養学科 2024 年 3 月卒業 奈良県立香芝高等学校出身 就職活動期間:2022 年 10 月 〜 2023 年 7 月 |
小学校の時、授業で食品添加物について調べたことがきっかけで食と栄養の分野に興味を持ちました。 普段何気なく食べているものにもさまざまな添加物が含まれていることに驚き、それ以降、食品表示を見るようになりました。 学んだことを身近なところで活かせるのが嬉しく、さらに食に関する知識を増やしたいと思って管理栄養士をめざすようになりました。
就職先の業種を選んだ理由
もともと医療職に興味があり、病院で働きたいと思っていました。最初は漠然とした憧れのような気持ちでしたが、大学で学んでいく中で、人間がごく当たり前に行う「食べる」ということを活かして治療を進めることの大切さに気付きました。さらに、実習で現場を見たことから病院で働きたいという想いがより強くなり、自分の意志が固まっていきました。
私の就活キーワード
「一歩一歩、少しずつ」
活動当初は腰が重く、就活に積極的な方ではありませんでした。「大変そう」「難しそう」といったイメージが大きかったからだと思います。 ただ、とりあえず説明会やセミナーには出席して情報を得たり、自己 PR や履歴書を書いてみるなど、就活に対するハードルを下げ、一つずつタスクを減らしていきました。 面接練習もはじめは緊張して思うように話せませんでしたが、改善点を意識しながら何度も練習し、最後には「1 回目からすごく成長したね!」と褒めていただき、内定にまで繋げることができました。
就活と聞くととてつもなく大きい壁に感じますが、早めの時期から一つずつやるべきことをこなしていけば、そこまで恐れるものではないなと実感しました。
 |  |  |
そして、その積み重ねの中で自分自身も大きく成長できたと思います。
就活のまっ只中にいる時は、そのことにあまり気付いていませんでしたが、終わって振り返ると、一つ一つは小さなことであっても、総じて見ると大きい成長だったと感じます。
心がけたこと、大変だったこと
私は大学が自宅から遠く通学時間が長かったため、電車の中などのすきま時間を無駄にしないよう心がけました。家でしっかり時間を取って作って取り組むのが一番かもしれませんが、授業の課題や国試の勉強などすることがたくさんあるので時間の有効活用はとても大切だと思います。通学中にスマホでエントリーを済ませたり、自己 PR を考えたり、私の場合は電車の中の方がむしろ捗っていたような気がします。
大変だったのは、就活のルールやシステムを理解し、それに慣れることです。初めてのことなので誰もが分からなくて当たり前なのですが、耳にする言葉も環境も、慣れないことばかりで苦労しました。 また、同時に複数のことを進めなければならない時期は、タスク・スケジュール管理が大変でした。
周囲のサポート
進路支援センターでは、就活に関して必要なことを、一つひとつ丁寧に、理解できるまで教えて頂くことができました。学生個々にしっかり時間を作ってくださるので、履歴書の添削から、自分では見つけられなかった求人情報の収集など、一人ひとりに合ったサポートを受けられる環境だと思います。面接練習で壁にぶつかった時期にキャリアコンサルタントの方が悩みや不安を優しく聞いてくださったり、最後の面接練習の後に職員の皆さんがエールの言葉をかけてくださったりしたことも、とても嬉しかったです。一緒に就活を乗り越えようとしてくださっているのが伝わり、精神面でも支えになったと感じています。
また、同じ時期に就活を頑張ってきた友人たちも、いい刺激を与えてくれ、励みにもなる存在でした。自分の内定が決まった時には一緒に喜んでくれて、友人の内定が決まった時は自分のことのように嬉しかったのは、大学生活の良い思い出の一つです。
 |  |  |
今後に向けて
まずは働く中で学べることをたくさん吸収し、病院で働く上で必要な知識を増やしていきたいです。栄養指導をする際などは、数字や専門用語ばかりではなく、実践しやすいように具体的な食品を挙げてみるなど、患者さん目線で指導のできる管理栄養士でいることを心がけたいと思います。
また、配属先の病院が先進的かつ国際的な病院をめざしており、限りなき挑戦を理念として掲げているので、私もさまざまなことに挑戦し、患者さんや病院に貢献できる管理栄養士になりたいです。
就活生へのメッセージ
私もそうでしたが、これから就活の時期を迎える方も、高い壁を感じているかもしれません。ただ、そこで後回しにし続けるのではなく、ひとまず進路支援センターに行って軽く話をしてみたり、説明会に一つだけ参加してみるなど、小さなきっかけを重ねていくことはとても大切だと思います。進路支援センターでは、2 年次頃から就活セミナーなどが開かれるので、参加していくと基礎知識がつき、いざ就活という時期に、よりスムーズにスタートをきれると思います。
将来、大阪青山の先輩かつ管理栄養士としてどこかでお会いできるのを楽しみに私も頑張るので、皆さんも目標に向かって頑張ってください!
【子ども福祉】三國 琴音 さん 社会福祉法人 あおば福祉会
 | 健康科学部 健康栄養学科 2024 年 3 月卒業 兵庫県立川西明峰高等学校出身 就職活動期間:2023 年 7 月 〜 8 月 |
体調を崩して何も食べられなくなった時があり、食の大切さを実感しました。その経験を通して、同じように病気の患者さんを食でサポートできるようになりたいと思い、食と栄養の分野に進みました。
就職先の業種を選んだ理由
管理栄養士の勉強をしていく中で、小さい頃からの食育の大切さを感じました。子どもたちが生きていく上で前向きに食と関わって行けるよう、乳幼児期からの食育に携わりたいと思い、保育所の管理栄養士をめざしました。
私の就活キーワード
「自信」です。
就職試験の際、面接官の方々は想像していたよりも優しく、褒めてくださることが多かったので、そこから自信を得ることができました。しんどいこともありましたが、常に笑顔でいることを心がけ、前向きに活動を進めてきたことが、望む内定へとつながったと思います。
面接では、志望動機や目標だけでなく、職種に関係する専門知識について問われることもあります。私の場合、乳児期の食育について訊かれることが多く、もっと詳しく勉強しておけばさらに自信がついたのではないかと思います。
 |  |  |
進路支援センターのサポート
まず、自分に合った就職先を一緒に探すところから、サポートして頂きました。めざすところが決まってからは、過去に就職試験を受けた先輩の面接状況などを詳しく教えてくださるなど、対策面でもしっかり支えて頂いたので、就職活動全般を通してお世話になったという感じです。
今後の目標・メッセージ
管理栄養士の資格があれば、幅広い業種にチャレンジすることができます。その一方で、求められる専門性が異なるため、準備が大変な面もあります。自分が行きたいと思った業種を諦めないでいいように、どの分野も早い段階からしっかりと勉強しておくことが大切だと思います。
それから、就活に行き詰まったと感じた時は、趣味に没頭して何も考えない時間を作ることも大事です!
子ども教育学部 子ども教育学科
【初等教育】田中 保乃美 さん 大阪府公立小学校
 | 健康科学部 子ども教育学科(現 子ども教育学部 子ども教育学科) 2024 年 3 月卒業 私立大阪高等学校出身 |
小学校でクラスを受け持ってくださった担任の先生に憧れ、自分も同じように小学校の先生をめざそうと思うようになりました。
就活で活かされた経験
教育実習でお世話になった小学校で、学習サポーターとして活動していました。おかげで、現場にいなければわからない小学校の中の様子をたくさん知ることができました。活動内容について面接で訊ねられることもあり、経験を踏まえてしっかり答えられたことが、大きな自信につながりました。
私の就活キーワード
「備えあれば憂いなし」
学習サポーターとして経験を積んだこともそうですが、学習面でも計画を立ててしっかりと勉強し、面接は先生方に指導を受けて対策を練るなど、たくさん準備をして試験に臨んだことが合格につながったのだと思い、この言葉を選びました。
試験は 5 教科あって範囲も広く、どれだけ勉強しても追いつかない不安感もありましたが、先生方の支えもあってなんとかやって来られました。
模擬試験に向けたアドバイスをくださったり、面接練習に何度も付き合ってくださったりといったサポートには、心から感謝しています。
 |  |  |
今後の目標・メッセージ
大学で学んできたことやボランティアの経験を生かし、子どもたちとしっかり向き合うことのできる教員になりたいです。
就活を頑張っている在学生の皆さんには、今取り組んでいることは将来助けになってくれるものなので、手を抜かず、全力で頑張ってほしいと思います。応援しています!
【幼児教育】福井 あゆみ さん カトリック聖マリア幼稚園
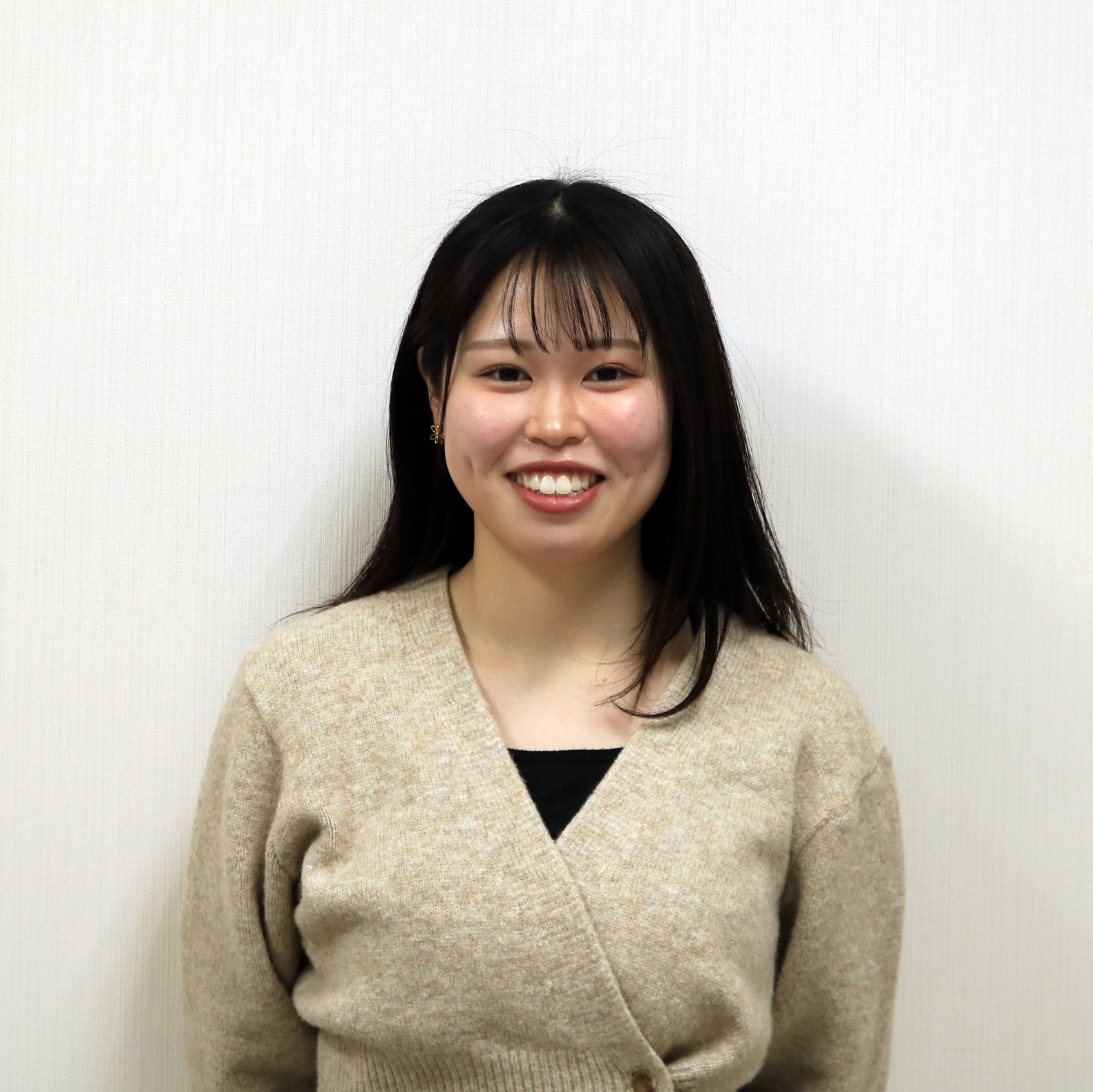 | 健康科学部 子ども教育学科(現 子ども教育学部 子ども教育学科) 2024 年 3 月卒業 大阪府立東淀川高等学校出身 就職活動期間:2023 年 7 月 |
小 1 の時の担任の先生への憧れから、小学校の先生になりたいと思うようになり、保育・教育の分野に進むことを決めました。言ったことには責任を持ち、いつも笑顔で明るくて、会うとどんな時でも元気になれる、今でも私の理想の先生像です。
就職先の業種を選んだ理由
ずっと小学校の先生になりたいと思っていましたが、さまざまな実習を経験していくうちに、自分の中でさらに具体的に何をしたいのか、どのような先生になりたいのかがわかってきました。
私は、たくさんお話ししたり、遊んだり、制作をしたり、新しいことを学んだり、子どもたちとより長い時間、近い距離で深く関わり、目一杯愛を伝え、その中で子どもの個性を伸ばし、集団生活の中でも居場所を作り、一人ひとりが輝けるように支えたいと思い、幼児教育を選びました。
 |  |  |
園選びのポイント
就職先の園を選ぶにあたり、自分のなりたい先生像やしたいことと園の方針が合っているか、先生同士、園の雰囲気が良いかどうか、といったことを重視しました。こういった情報は、待っているだけでは得られないことが多いので、自ら行動し、知りたいことや気になることを、自分で確かめるよう心がけました。
もう少し調べておけば良かったと思ったのは、ピアノについてです。私はピアノが苦手なので、普段の保育でどれくらいピアノを弾くか、難しい曲を弾く機会が多いかなど、もっと詳しく見ておけばよかったなと思いました。制作が苦手な人は、壁面制作がどのように作られているのかなどを見ておくと良いかも知れません。
周囲のサポート
園のことを詳しく調べたい時、また、どうやって選べば良いか迷った時には、学科の先生方や保育・教職支援室のスタッフの方が、その都度必要な情報やアドバイスをくださいました。園からの求人票には書かれていないことや、先輩の面接の記録など、詳しい情報が役に立ちました。先生方も、保育・教職支援室も、訪ねて行けばいつもたくさんのことを教えてくださいます。わからないことや困ったことがあった時に、気軽に聞きに行ける場所があることは、大きな支えになりました。
先生方も友だちも、みんなで頑張ろうという雰囲気があり、自分は一人じゃないという安心感をもって就職活動を進めることができました。
今後に向けて
子どもの成長に携わることができること、成長を近くで見られることを、とても楽しみにしています。
幼稚園では、子どもの成長に良い影響を与えられるような環境・活動を通して、子どもたちの居場所を作り、そこから個性を伸ばすことができるように支えていきたいです。
私が子どもの頃に憧れた先生のようになり、そしてまた、子どもたちにも「先生っていいな」と思ってもらえたら嬉しいです。
就活生へのメッセージ
実際に社会に出て働く時が近づいて来ると、不安だったり、どこに就職したいか悩んだり、何がわからないのかもわからない時があったり、大変だと思います。その時は、うまく言葉にできなくても、保育・教職支援室や先生方に伝えると、必ず助けてもらえます。ヒントやアドバイスをたくさんもらい、自分の中の答えに近づくことができるので、一人で抱え込まず、周りに頼って相談してください。
就職のことだけでなく、たくさん悩みがあったり、忙しかったりする時期だと思いますが、今を目一杯楽しんでください!
【子どもの福祉】八木沼 芳子 さん 社会福祉法人神戸婦人同情会 子供の家
 | 健康科学部 子ども教育学科(現 子ども教育学部 子ども教育学科) 2024 年 3 月卒業 大阪府立島本高等学校出身 就職活動期間:2022 年 11 月 〜 2023 年 6 月 |
子どもと関わることが好きで、保育専門コースのある高校に進みました。そこで幼稚園や地域の子どもと多く関わり、保育についてより興味を持つようになりました。
就職先の業種を選んだ理由
大学の授業で児童福祉について学び、辛い思いや経験をしてさまざまな課題を抱えた子どもたちがたくさんいることを知りました。そうした子どもたちが明るい未来へ自分らしく踏み出して行くための支援をしたいと思うようになり、福祉の分野に進むことを決めました。
心がけたこと、大変だったこと
施設の基本理念や支援方針が、自分のなりたい保育士(職員)の姿に沿っているか、調べるようにしました。施設の環境や、職員と子どもとの関わりを実際に見てみると、自分の抱いていた施設に対するイメージが変わることもありました。就職活動を進めるにあたり、実習やアルバイトでの経験が大いに参考になったので、現場を知る機会をつくることは大切だと思いました。
大変だったのは面接対策です。志望動機や、こんな風に子どもと関わりたい、といった思いが自分の中にあっても、いざ文章にして相手に伝えようとするとうまく表現できず、難しさを感じました。自己分析や大学生活の振り返りも、改めて考えてみると行き詰まることが多く、苦労しました。
周囲のサポート
困った時、保育・教職支援室のスタッフの方々に必要書類の書き方等を確認していただけたのは、とてもありがたかったです。就職活動を進めるうえで、今しなければならないこと、次にするべきことを、一つひとつ順を追って丁寧にサポートしてくださるので、安心して取り組むことができました。
学科の先生には、実習先で気になった施設のアルバイトを勧めて頂き、子どもとの関わりかたなどで困った時は、アドバイスをもらうこともありました。
保育・教職支援室はもちろん、先生との距離も近いので、すぐに相談できる場所がたくさんあり、心強かったです。
 |  | 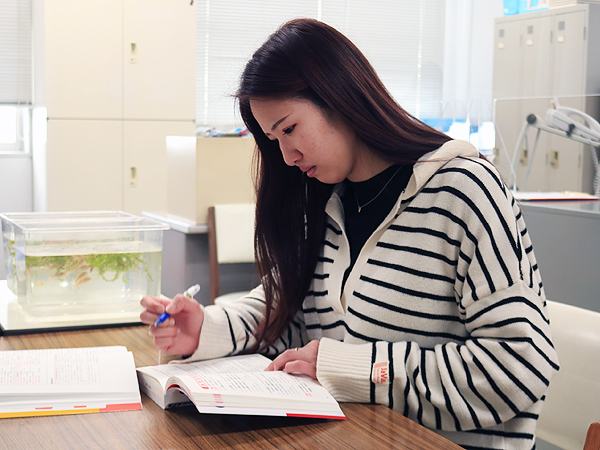 |
私の就活キーワード
「繋がり」
就職が決まった時、自分も社会福祉に携わることができるという実感が湧いて嬉しかったです。実習がきっかけで施設のことを知り、その後アルバイトとしても関わることができました。このことがきっかけで、より近くで職員と子どもとの関わりを見たり、業務内容に触れたりすることができ、志望意欲が高まりました。今では、一つひとつのステップが繋がっていたと感じています。
今後に向けて
これから、学生時代よりも多く子どもと関わることができるのが楽しみです。大学で培った知識や経験を、現場で生かす時が来たという期待感もあります。子ども一人ひとりの発達や姿に寄り添って、課題を共に乗り越えていきながら、彩り豊かな生活を支援していきたいです。
そして、子どもたちが人生を振り返った時に、私がいてくれてよかったと思ってもらえるような職員になれるよう頑張りたいです。
 |  |  |
就活生へのメッセージ
後悔のないよう、気になる園や小学校、施設があれば自分でたくさん調べたり、先生や友だちを頼って多くの情報を得るようにしてください!!納得のいく就活になるよう、応援しています。
看護学部 看護学科
中谷 光 さん 東京慈恵会医科大学附属病院
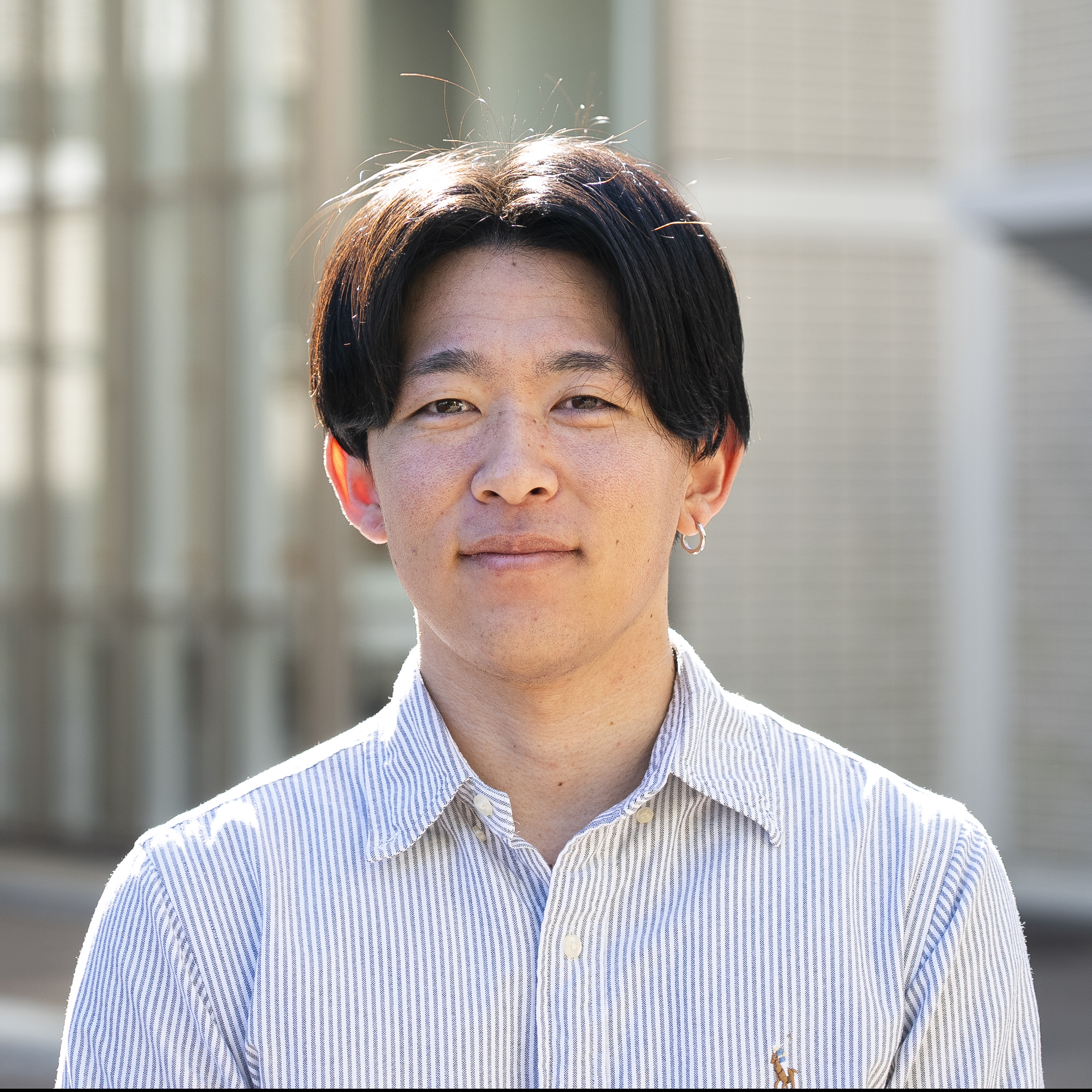 | 健康科学部 看護学科(現 看護学部 看護学科) 2024 年 3 月卒業 広島県立尾道高等学校出身 就職活動期間:2022 年 11 月 〜 2023 年 4 月 |
人の手助けを行える人間になりたいという思いから、人の想いと常に向き合い、支えることができる存在である看護師をめざしてきました。
就職先の病院を選んだ理由
病院の理念である「病気を診ずして病人を診よ」に感銘を受け、さらに、実習を通して病院の精神が自分の看護観と一致していることを実感。特定機能病院であり、1,000 床以上の大きな規模を持つことから、高度な技術・知識を身につけられるという点も魅力で、ここを目標にしようと決めました。
私の就活ポイント
沢山の病院がある中で、まずは自分の看護観や、将来どのようになりたいかといったことを自己分析し、それが叶う、活かせるような病院かどうかということを病院探しのポイントにしてきました。気になる病院の説明会に参加したり、パンフレットなどから情報収集をする際にも、そういった点を特にしっかりと見るよう心がけました。
大変だったことと周囲のサポート
大学の進路支援センターでは、自分の長所短所から、看護観や将来なりたい自分などについて客観的かつ的確なアドバイスを頂き、自己分析に役立てることができました。履歴書の限られた小さい枠の中で自分の思いを表現するのはとても大変でしたが、伝えたいことを言語化してわかりやすい言葉に置き換えてくださるなどのサポートに、とてもお世話になりました。
また、自分の背中を押してくれる家族や、同じように大学病院をめざしていた友人、小論文を最後まで見てくださった先生など、常に周囲の人に支えられながらの就職活動でした。
 |  |  |
今後に向けて
自分が望んで就職できた病院で、これから経験できる全てのことを楽しみにしています。
まずは一人前の看護師になること、そのためにしっかりとした知識や技術を身につけ、どんなことにでも対応できるようになりたいです。そして、将来的には認定看護師や専門看護師などをめざしたいと考えています。
就活生へのメッセージ
自分が行きたいという気持ちがあれば、病院の規模は関係ありません。沢山選択肢がある中で、迷うかもしれませんが、本当に行きたいと思ったところにぜひ挑戦して、後悔のない就活をしてください!
上田 奈未 さん 奈良県立医科大学附属病院
 | 健康科学部 看護学科(現 看護学部 看護学科) 2024 年 3 月卒業 奈良県立橿原高等学校出身 就職活動期間:2023 年 4 月 〜 5 月 |
看護師をしている母の影響で小さい頃から看護に触れることが多く、働く看護師の姿を見て「かっこいい!」「私もこうなりたい!」と、4、5 歳の頃から思っていました。その時からずっと、看護師を志しています。
頑張ったこと、大変だったこと
就職先となる病院は、高校生の時に看護体験に参加して雰囲気がよかったこと、奈良県では一番大きな病院で、高度な技術や知識を身につけられると考えたことから、ずっと目標にしてきました。
大学に入った時からその目標を見据え、勉学に一生懸命取り組んできました。
しかし、いざ就活準備となると「自分の長所・短所」や「どのような看護師になりたいか」など、なんとなく考えてはいても、言語化するのが大変でした。自分を客観的に分析すること、自分自身を見つめ直すことが難しく、毎日面接のことを考えて緊張状態が続きました。とてもしんどい時期でしたが、この経験を通して自分の癖や特徴を知ることができました。
周囲のサポート
進路支援センターでは、エントリーシートから面接、小論文作成に到るまで、丁寧なサポートを受けることができました。
改善点があれば具体的に教えて頂き、また面談などを通してまざまな方向から質問をしてもらうことで、自分の考えがまとまって行きました。
スタッフの方々はいつも親身になって対応してくださり、内定が決まった時は自分のことのように喜んでくださいました。就職活動を進めて行く上で欠かすことのできない、心強い存在でした。
また、周りの友人たちも同じ時期に就職活動をしていたので、大変さを分かち合えたことが心の支えになりました。お互いにメッセージを書き合い、面接前に見て心を落ち着かせたこともありました。
無事内定をもらった時は、憧れていた病院から必要としてもらえることをとても嬉しく感じました。
 |  |  |
今後の目標・メッセージ
大きな病院でたくさんの経験を積み、スキルアップできることを目標としています。
同期入職が 100 名ほどいるので、仲の良い人を見つけて交流するのも楽しみです。
これから就職活動に取り組む人は、まず色々な情報を手に入れることをお勧めします。
そして、辛いことや大変なこともあると思いますが、友だちと支え合って乗り越えてください。









