OAU Talk! 子ども教育学科
テーマについて語る「保育と教育の連結」

 | 子どもの未来を創る仕事です。 子どもを知ることは、自分を知ることでもあります。自分を大切にしながら、子どもも大切にできる素敵な先生として、大阪青山大学の卒業生が活躍してくれることが、私たちの願いです。そのためには、厳しさの中にある優しさ、正しさ、清らかさ、強さが大切です。私も自分自身が幼稚園教諭だった経験を活かして、精一杯みなさんの頑張りをサポートします。ぜひ子どもへの優しさを持った先生になってください。 |
| 子ども教育学部 学部長 戸松 玲子 教授 | |
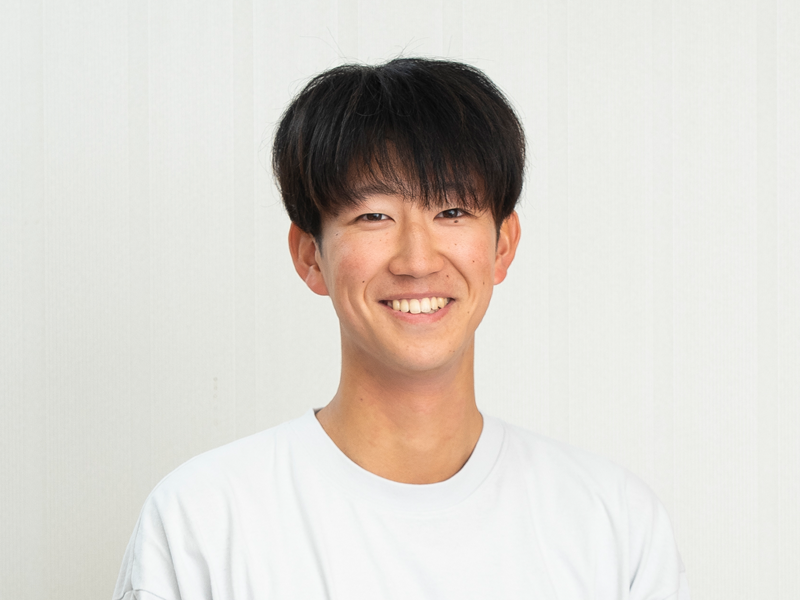 | 小学校の先生をめざしています ! 模擬授業のための指導案を作成していますが、自分が教壇に立って子どもたちに教えているところを想像するとワクワクします。また大阪青山大学に入学してから、教育と福祉がなぜ連携するべきなのか、といった新たな視点を持つことができ、入学前よりも、自分がめざすべき先生像がよりはっきりしてきたことを実感し、充実した毎日を送っています。 |
| 子ども教育学科 2 年次 中司 涼太 | |
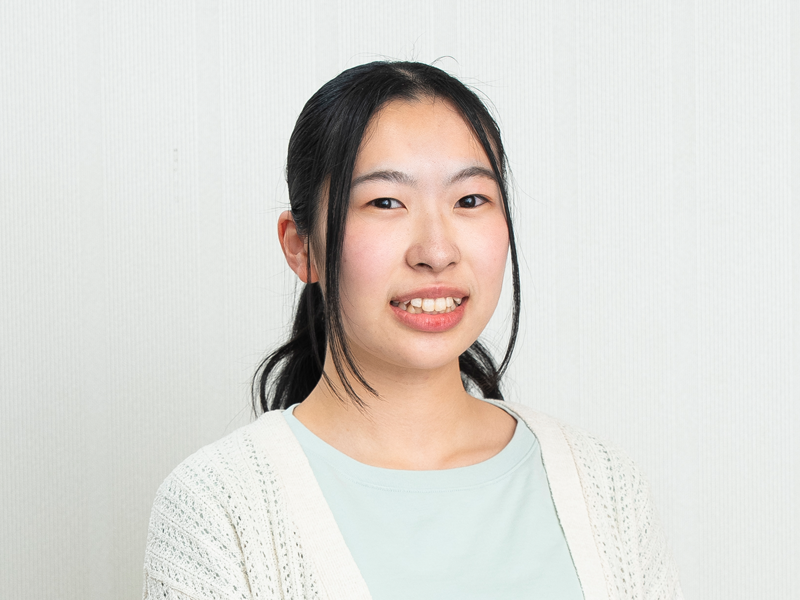 | 幼稚園の先生をめざしています ! オープンキャンパスに参加した際、学部長である戸松先生のミニ講義を聴き「是非こんな授業を受けて学びたい」と思ったことが入学の理由です。授業の内容だけでなく、少人数制で一人ひとりをきめ細かく指導してもらえる体制など、人見知りな性格の私でもしっかりと学べる環境が整っていて、大阪青山大学でなら、幼稚園の先生になるという自分の目標に向かって、安心して頑張っていけると感じています。 |
| 子ども教育学科 1 年次 島林 胡音美 |
戸松:中司さんが本学に入学した理由は、保幼小の3資格同時取得ができるのが大きかったということですね。そういう学校は他にあまり無かった?
中司:そうですね。あまり無くて。僕がめざしているのは小学校の先生なんですけど、三つも資格が取れるなら、履歴書にも書けるし良いなと思って。
戸松:島林さんは元々幼稚園の先生になりたかったんですよね。いつ頃から思ってたの?
島林:小6くらいの頃ですね、下級生の子たちと遊ぶのがすごく楽しくて、その頃からぼんやりと思い始めたんですが、その気持ちがそのまま今も続いている感じですね。
戸松:そうなんですね。二人にとって、大阪青山大学の魅力はどういうところだと思いますか?
中司:先生方のご経験ですね。例えば小学校教諭をめざすための授業なら、実際に元小学校教諭をしていた先生が教えてくださいます。経験者の方の考えや意見を聞けるのが魅力です。
戸松:そうですね。これは実は大阪青山大学の特長です。例えば、小学校教諭として理科を専門に研究していたり、社会科を研究していたり、という人に先生になってもらっています。これはほかではあまりなく、本学の強みだと思いますね。
島林:そうですよね、私も入学してみて、すごく専門的に学べるということに驚きました。それと、先生との距離が近くて話しやすいというのが嬉しいです。私は人見知りする性格なんですけど、授業で分からない点があっても、すぐに質問できる距離感がすごくいいなって思ってます。


戸松:確かに学生と先生の距離感は近いですね。近すぎて友達みたいにならないように気をつけてますけど(笑)ところで、いま二人が頑張っていることは?
中司:僕は実習ですが、難しいと感じるのは距離感です。言葉遣いひとつでも、子どもは敏感に反応するので、ちょっとしたことに気づける先生になりたいと思っています。
島林:私は勉強したことを実践に出すのがあまり得意じゃないので、よりちゃんと自分の中に落とし込んで、それを出せるようにしたいです。
戸松:私たちも今でもそういうことはあって、永遠の課題ですよね。私が今後より大切になると考えているのは、教育と福祉です。福祉というと、例えば施設に入っている子どもというイメージがあるかもしれませんが、実は在宅支援の子がほとんどで、学校の先生が引き受けなければいけない状況になってきている。そういった中、大阪青山大学で教職をめざすカリキュラムには、福祉関連の科目が卒業必修に据えられているというのは、とても大きな意味があるんです。
島林:先生は第三者目線で保護者と子どもを見られる立場だからこそ、福祉をちゃんと理解してサポートできるようにしないといけないというのは、どの授業を受けていても感じますね。
戸松:教育の究極の目標というのは自立です。福祉も弱い人の自立を支援するということなので、教育と福祉のめざすところは一緒だし、もともとの学校の成り立ちはそこなんですね。では最後に、今後の目標は?
中司:僕は小学校の先生です。何かあったら中司先生に言えばいいと思ってもらえる先生になりたいですね。
島林:私は幼稚園の先生なんですけど、子どものことをしっかり見て、小さな変化や成長をちゃんと見ていける先生になりたいなって思ってます。
戸松:じゃあ二人とも、大阪青山大学のカリキュラムがぴったり合ってますよね。本学の卒業生が関わった子どもたちが幸せになって、大人になって、いい人生を歩む。そしてその子たちがまた幸せを生んでくれるために… 少し壮大ですけど(笑)それが私たちのめざしているところなんです。それを授業で感じてもらえているといいなと。
中司:日々、しっかり感じています!
島林:(笑)

[年次は取材時]

